OFFICAL ACCOUNTFOLLOW US
TOPICS
昭和22年創刊、800号を迎えたニッタクニュースのバックナンバーから編集部がピックアップしてお届けするページです。
※ここに紹介の記事は、原文を一部抜粋、編集しています。敬称略
QアンドAとエピソードでつづる世界選手権おもしろ史
第37回大会1983(昭和58)年4月28日-5月9日 東京(日本)
二度目の東京開催で大会運営と審判員養成は成功したが、卓球ブームの再来はあったか?
女子団体でKOREA破り2位に
――東京で二度目の開催だが、日本に前回(56年)のような卓球ブームの再来があったの?
……卓球ブームの再来は、なかった。地元で王座奪還が期待されたが、前大会より、一歩前進の「女子団体2位、男子ダブルス3位」の成績をあげたけれど、中国の強さが目立つ大会で終わった。斎藤清・前原正浩を中心に男子ダブルスの優勝をねらう、という基本方針だったが、ふたりともシングルスの練習のほうが多かったようで、斎藤組が準々決勝で中国ペアに惜敗し、小野誠治・阿部博幸組の3位入賞どまりで、金メダルにいたらなかった。そうした中で光ったのが、神田絵美子と新保富美子の大活躍により、韓国・北朝鮮という二つの強豪を破って、女子団体で2位を確保したことだった。特に、この大会の女子シングルスで2位となる梁英子(韓国)をふたりとも破ったのは圧巻だった。神田が4番で梁を最終ゲーム22-20で破って日本に勝利をもたらした瞬間は、国立競技場代々木第一体育館が興奮と感動につつまれた。地味だが、新保のダブルスパートナー田村友子の凡ミスのないカットも光った。神田のドライブ、新保のカットと攻撃は、まさに一級品であった。
競技を離れて、少し述べると――。現在の天皇・皇后両陛下が皇太子妃時代に最終戦をご覧になったこと。エバンス国際卓球連盟会長から「大会運営はすばらしかった。今大会の特徴の一つは、コンピューターを導入し、ものすごく速く試合結果を流したことである」との評価があったこと。日本開催が決まった時には3名しかいなかった国際審判員が、日本卓球協会関係者の努力で世界最多の167名の資格者を輩出し、そのうち124名が審判員として協力したこと。オリンピック旗が“白い風”(大会テーマ曲)にのって、世界選手権で初めてかかげられたこと、などがあった。
余談-日本がベストワン
競技面では、残念ながら日本の金メダルはなかった。だが、別の面で日本がベストワンに選ばれた。それは、アメリカと東京の両方のオフィスに卓球台を持ち、卓球台でポスターづくりなどを行うアートディレクターの靉嘔(あい おう)が制作した大会ポスター。国際卓連によって過去57年間の世界選手権史上における“ベストポスター”に選ばれた(日本卓球協会が中心となった大会組織委員会(会長高城元・日本卓球協会会長)が企画製作。大日本印刷等が協力した)。
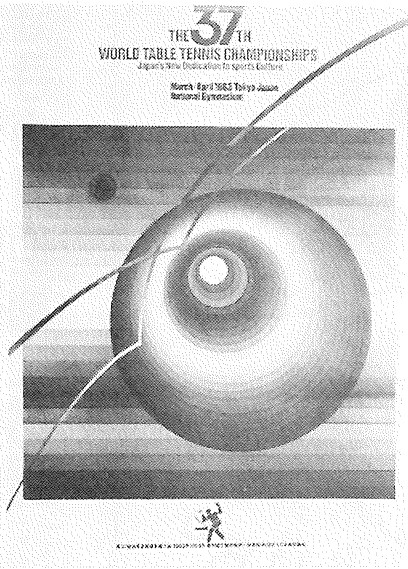
●こぼれ話
“Mrフットワーク“の逆立ち
中国が6種目に優勝したが、男子ダブルス決勝の顔ぶれを見た大会関係者の多くは、2大会連続して、中国の完全優勝と思った。謝賽克・江加良組対シュルベク・カリニッチ組(ユーゴ)の対戦だが、すでに男子シングルスで謝はシュルベクに、江はカリニッチに勝っているからである。だがユーゴ組のコンビネーションがすばらしく最終ゲームを22対20で勝ってスタンドを沸かせた。勝利の瞬間にシュルベクは逆立ちをし、そのあとカリニッチと抱き合って喜びを表現。卓球界で“Mrフットワーク”といわれた選手が日本の木村興治とシュルベクのふたりいるが、共にダブルスの名手であった。
【各種目優勝者】
男子団体:中国(江加良・謝賽克・蔡振華)
女子団体:中国(曹燕華・耿麗娟・倪夏蓮)
男子単:郭躍華(中国)
女子単:曹燕華(中国)
男子複:シュルベク/カリニッチ(ユーゴスラビア)
女子複:沈剣萍/載麗麗(中国)
混合複:郭躍華/倪夏蓮(中国)
藤井基男(卓球史研究家)
1956年世界選手権東京大会混合複3位。引退後は、日本卓球協会専務理事を務めるなど、卓球界に大きく貢献。また、卓球ジャーナリストとして、多くの著書を執筆し、世に送り出した。特に卓球史について造詣が深かった。ニッタクニュースにおいて「夜明けのコーヒー」「この人のこの言葉」を連載。
本コーナーは藤井氏から「横浜の世界選手権に向けて、過去の世界選手権をもう一度書き直したい」と本誌編集部に企画の依頼をいただいた。執筆・発行の14日後、2009年4月24日逝去










